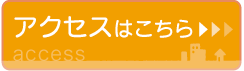耳の病気
急性中耳炎
鼓膜の内側の中耳腔という場所に炎症が起きて、耳の痛みや聞こえが悪くなるなどの症状を起こします。鼻側の細菌やウィルスが中耳にまで及ぶことが主な原因とされており、かぜの時に多く、またアレルギーによる鼻炎やアデノイドの炎症なども影響を与えます。一般に、鼻と耳を結ぶ耳管の機能が未熟な小児に多くみられます。治療は抗生物質の内服と鼻炎の治療で回復するのが一般的ですが、炎症が大きいと鼓膜から小さい穴があいて耳だれが出たりすることもあります。炎症を繰り返したり、中耳腔に貯留物が残存する滲出性中耳炎に移行したりすると、治療が長引くことがあります。
滲出性中耳炎
鼓膜の内側の中耳腔という場所に液体がたまり、聞こえが悪くなることもあります。耳と鼻を結ぶ耳管の機能が未熟な小児期に多いですが、悪い状態を放置すると耳の発育成長に悪影響を及ぼし将来的に慢性中耳炎や真珠腫性中耳炎などの原因となることがあります。
治療は、鼻炎・小児副鼻腔炎、のどの治療を一体におこなっていくことが大切で、週から月の単位で通院を要することも少なくありません。一般には、鼻腔の吸引処置、鼻から空気を入れて耳の換気をはかる耳管通気、その部分へ薬を吸入するネブライザー療法などが一般的です。経過が悪い場合は、鼓膜を切開して貯留液を吸引したり、鼓膜換気チューブ挿入術をおすすめすることがあります。
治療は、鼻炎・小児副鼻腔炎、のどの治療を一体におこなっていくことが大切で、週から月の単位で通院を要することも少なくありません。一般には、鼻腔の吸引処置、鼻から空気を入れて耳の換気をはかる耳管通気、その部分へ薬を吸入するネブライザー療法などが一般的です。経過が悪い場合は、鼓膜を切開して貯留液を吸引したり、鼓膜換気チューブ挿入術をおすすめすることがあります。
真珠腫性中耳炎
鼓膜の内側の中耳に皮膚の一部が入り込み、その落屑物が真珠のような塊となって、耳の骨などを壊していくという病気です。生まれながらの先天性真珠腫もありますが、多くは、耳管機能不全、滲出性中耳炎、慢性中耳炎など中耳の換気が悪い状態が続くとことが主な原因とされています。放置すると耳漏、難聴、めまい、顔面神経麻痺、髄膜炎などを起こすことがあります。治療には定期的な耳処置と感染のコントロールが不可欠です。緩慢な経過をたどることが多いですが、進行したケースでは手術が必要です。
慢性中耳炎
大人に多い中耳(鼓膜の内側)の慢性炎症ですが、耳だれなどをくり返して徐々に難聴となる場合があります。幼少期に反復性中耳炎や滲出性中耳炎の状態が続いたりすることが主な原因です。
外耳炎
鼓膜の外側である外耳道に起こった炎症です。頻繁な耳かきによって起こることも多く、悪化すると耳全体が腫れることもあります。炎症やかゆみをおさえる点耳薬や軟膏を中心に治療しますが、耳を触らず安静にすることも大切です。
外耳道真菌症
鼓膜の外側である外耳道にカビ(真菌)がついて痛みなどが起こる病気で、外耳炎が背景にあることも多いです。治療は耳外耳道の掃除をして炎症やカビを抑える薬を塗りますが、単なる外耳炎よりも治療に時間がかかることも多く、こまめに通院を要する場合があります。
外耳道異物
耳の穴に虫や玩具などが入ってしまった状態です。こどもがふざけて耳におもちゃなどを入れてしまい取れなくなったり、就寝中などに虫が入ってくることもあります。無理に取ろうとすると、耳を傷つけたり(外耳炎)、ますます取れなくなったりすることがありますので、耳鼻咽喉科の受診をお勧めします。
反復性中耳炎
鼓膜切開を要する重い急性中耳炎をくり返した(半年に3回、年に4回以上)状態です。3歳以下の集団保育を受けるお子さんに起こりやすい病気です。治療は抗生剤の内服や鼓膜切開が中心ですが、鼓膜換気チューブ挿入術をおすすめすることがあります。
耳垢栓塞
過剰の耳垢(みみあか)が外耳道に溜まった状態です。少量の耳垢は正常ですが、溜まりすぎると痒みの原因となったり聞こえが悪くなることがあります。外耳道が狭くて掃除しずらい、お子さんが掃除させてくれないなど、耳掃除が難しい場合は耳鼻咽喉科の受診をお勧めします。
突発性難聴
突然、聞こえが悪くなる病気です。めまいを伴うこともあります。原因ははっきりしていませんが内耳神経のウィルス感染や血流障害などの説があります。治療が遅れると極めて治りにくくなりますので、数日以内に耳鼻咽喉科の受診をお勧めします。聴力検査を受けていただき、必要があればステロイド剤などで治療します。
加齢性難聴(老人性難聴)
年齢とともに徐々に進行する難聴ですが、左右とも同程度に低下していきます。一般に治療は困難ですが、生活に支障が大きい場合は補聴器をお勧めします。加齢により言葉の理解が低下することも多いため、周囲の方の理解と配慮も大切です。
騒音性難聴
騒音環境に長くいることで少しずつ内耳がダメージを受け、難聴となった状態です。聴力検査で4000Hzだけが聞こえにくいのが典型的な所見ですが、治療は困難です。難聴を進行させない環境整備が大切になってきます。
音響外傷
急に大きな音を聞いてから聞こえが悪くなったり、コンサートなどの後で耳が詰まる感じがしたり、何かのきっかけで聞こえの神経がダメージを受けて難聴を来す病気です。大きな音を聞いた後から聞こえが悪い場合は、早めに耳鼻咽喉科を受診した方が良いでしょう。
機能性難聴
実際には聞こえの神経に問題がないのに、聴力検査で難聴となる状態です。聞こえないふりをする詐聴の他に、心の反応によって聴力低下を示す心因性難聴があります。心因性難聴では本人には悪気はないので、責めずにカウンセリングすることで徐々に回復することをめざします。
両側性特発性感音難聴
両側の聴力が徐々に悪化するもので原因不明の難聴の総称です。めまいや耳鳴を伴うこともあります。まずは一般的な難聴の治療を優先しますが、治りが悪い場合は精密検査の上この病気が疑われます。
耳硬化症
音を伝える耳小骨の動きが悪いために難聴となる病気です。聴力検査で特徴的な所見がみられますが、精査をして経過観察・補聴器・手術といった適応を決めていくことになります。
外リンパ瘻
内耳に空いた小さな穴からリンパ液が漏れ、めまいや難聴を起こす病気です。突発性難聴と似ていますが、典型例では、重いものを持ち上げたり鼻を強くかんだりした後に、弾けるような音がしたり水が流れるような音がします。難聴の治療に加えて安静療法が大切ですが、重症の場合は手術を要することもあります。
耳管開放症
耳と鼻をつなぐ耳管という細い管が開きっぱなしの状態です。自分の声や呼吸音が響いたり耳が塞がった感じが特徴です。体重減少、妊娠、加齢などの影響で、耳管の筋肉が痩せると起こりやすくなります。治療は体重の回復、点鼻薬、漢方薬、耳管処置などがあります。
耳管狭窄症
耳と鼻をつなぐ耳管という細い管の通りが悪く、耳が塞がった感じがします。鼓膜所見や聴力検査などで診断します。鼻から風を通す耳管通気という処置や、ネブライザー療法、内服薬、自己通気の実践などです。慢性化すると滲出性中耳炎を起こすことがあります。
耳性帯状疱疹(耳介帯状疱疹)
体内にいるウィルスが再活性化して、耳に帯状疱疹を起こすものです。難聴、めまい、顔面神経麻痺などを合併する(ハント症候群)こともあります。抗ウィルス薬、ステロイド剤などで早期に治療することが大切です。
ハント症候群
末梢性顔面神経麻痺のうち約20%を占め、顔面神経麻痺、内耳神経障害(難聴、耳鳴、めまい)、耳介帯状疱疹が特徴です。治療が遅れると後遺症を残しやすいので、抗ウィルス薬、ステロイド剤などで早期に治療することが大切です。
ベル麻痺
特発性片側性末梢性顔面神経麻痺のことですが、末梢性顔面神経麻痺の約2/3を占めます。体内にいるウィルスが顔面神経で再性化して、神経にメージを起こすと言われています。
眼が閉じにくい、口から水がこぼれるなど、顔の表情筋の動きが悪くなります。治療が遅れると治りにくいので、抗ウィルス薬、ステロイド剤などで早期に治療することが大切です。
眼が閉じにくい、口から水がこぼれるなど、顔の表情筋の動きが悪くなります。治療が遅れると治りにくいので、抗ウィルス薬、ステロイド剤などで早期に治療することが大切です。
耳性放散痛
耳を支配する神経と、鼻・口腔・咽頭などを支配する神経は重なる部分があるため、耳に異常がなくても鼻・口・のどに原因があると、耳が痛く感じることがあります。これが耳性放散痛です。原因を見つけるためには耳以外の診察も大切です。
骨部軟骨膜炎
耳の皮膚から入った細菌が軟骨までおよぶ炎症です。耳全体が赤く腫れてひどい痛みや高熱が出ることもあります。抗生剤を中心に治療します。外耳炎が原因のことも多く、注意が必要です。
聴神経腫瘍
内耳の神経にできる腫瘍ですが、徐々に難聴となる場合と突発性難聴のように急に難聴をきたす場合があります。診断にはMRIが有用ですが、腫瘍のサイズなどによって経過観察、放射線、手術といった適応を検討する必要があります。
外耳道癌
中高年に多い稀な病気です。慢性中耳炎や慢性的な外耳炎が影響を及ぼすともいわれていて、耳の痛みや出血、耳のつまり感が出ることがあります。組織検査で診断され、手術を念頭に治療を検討します。
三叉神経痛
顔の知覚を司どる三叉神経の何らかの異常によって、特定の部位に鋭い痛みがおこる病気です。帯状疱疹や急性副鼻腔炎、周囲の血管による圧迫、その他いろいろな原因によると言われています。治療は神経痛の内服薬が中心となります。
メニエール病
めまい、難聴、耳鳴りなどを繰り返す病気で、内耳のむくみが原因とされています。心身のストレスが関係するとも言われており、若年から中年の女性に多くみられます。診断は主に問診と聴力検査でおこないます。早期の治療開始が望まれ、難聴がひどい場合はステロイドを用いることがあります。
ウェゲナー肉芽腫症
鼻、耳、肺、腎臓などに障害を起こす免疫疾患です。鼻出血・鼻づまり・耳閉感などから疑われますが、血液検査などで診断され、薬物治療でコントロールしていきます。
流行性耳下腺炎(おたふく風邪)
ムンプスウィルス感染による耳下腺炎ですが、感染力が強く登校の制限なども決められています。稀ですが、ムンプス難聴という難治性の難聴にかかることがあります。おたふく風邪の治療は解熱剤などの対症療法が中心となります。
亜急性甲状腺炎
甲状腺が炎症を起こし、のどの痛み、圧痛、嚥下時痛などが生じる病気です。ウィルスの関与が言われていますがはっきりしていません。血液検査などを元に診断し、炎症を抑える内服治療をおこないます。
頚部リンパ節炎(炎症性リンパ節腫脹)
首のリンパ節が炎症を起こして腫れる状態です。首から上の部分(耳鼻のど等)に細菌感染などが起こると、感染をくい止めようとして、首のリンパ節が炎症を起こして腫れます。特に、子どもはリンパ節も未成熟のため、より腫れやすい傾向にあるので珍しいことではありませんが、腫れが引かないとか、次第に大きくなってくる場合は、リンパ自体の病気も稀にありますので、専門医にご相談ください。治療は抗生剤の内服あるいは何もしないで経過をみることも多いです。
亜急性壊死性リンパ節炎
発熱と首のリンパ節の腫れが数週間つづく病気です。臨床経過や血液検査などで診断します。ウィルス感染が原因と考えられていますが、はっきりしていません。治療は解熱鎮痛剤などの対症療法が中心ですが、ステロイド内服を併用することがあります。
良性発作性頭位めまい(頭位性めまい)
耳の奥の三半規管には位置感覚に関係する耳石が存在しますが、これが何らかの理由でズレることで生じるめまいと考えられています。難聴や耳鳴りを伴わない、数~数十秒の回転性めまいであり、頭を動かさないでじっとしていると治まり、動かすとまた起きることが特徴です。程度に個人差が大きいですが、めまいは時間がたつと治まってきます。症状がひどい時は内服や点滴を用います。
前庭神経炎
三半規管の情報を脳に送る前庭神経に何らかの炎症が起きて、持続的な回転性めまいを生じます。難聴や耳鳴りを伴いませんが、良性発作性頭位めまいとは違い、頭を安静にしてもめまいは軽快しません。安静が基本であり、症状がひどい時は内服や点滴を用います。
椎骨脳底動脈循環不全
小脳や椎骨脳底動脈の血液の供給が悪いことで起きるめまいです。めまいの他に神経症状がある場合は、この病気を疑う必要があります。頭部MRIなどで診断します。
起立性低血圧
起立時に脳への血液供給が少ないため、立ちくらみを起こす病気です。原因は、低血圧であったり、思春期で自律神経のバランスが未成熟な場合や、降圧剤、前立腺、安定剤などの薬剤の影響などが考えられます。血圧を測る検査で診断し、内服を中心に治療します。
脳脊髄液減少症
脳脊髄液が減ることで、起き上がる時などにふらつきや頭痛が生じる病気です。頭部外傷や出産後に起きることがあり、また神経症状も伴うことがあります。安静療法および注射など状態によって適切な治療が必要です。
頸性めまい
首をひねると、内耳への血流である椎骨動脈が細くなり、血液が行かなくなるため起きるめまいです。画像検査で原因を調べますが、首をひねらない習慣も大切になります。
上咽頭癌
鼻腔の突き当り付近である上咽頭にできる癌のことです。成人で滲出性中耳炎がある場合、上咽頭癌を除外することが大切です。鼻から内視鏡を入れて比較的容易に検査できます。
急性咽喉頭炎
いわゆる「のど風邪」とも言えますが、ウィルスや細菌感染などで咽頭や喉頭が炎症を起こした状態です。炎症を抑える薬など対症療法が中心ですが、細菌感染が疑われるケースでは抗生剤も検討されます。
急性扁桃炎
口蓋扁桃(俗にいう扁桃腺)の急性炎症です。口蓋扁桃は口蓋垂(のどちんこ)の両脇にあるリンパ組織ですが、ウィルスや細菌感染などにより炎症を起こして赤く腫れます。悪化すると扁桃周囲炎・扁桃周囲膿瘍・頸部膿瘍に進展することもあります。抗生剤を中心に治療しますが、伝染性単核球症のようなウィルス疾患では敢えて使用しないケースもありますので、耳鼻咽喉科専門医での診察をお勧めします。
慢性扁桃炎
急性扁桃炎をくり返す状態です。治療は抗生剤が中心ですが、基準以上に頻繁なケースでは口蓋扁桃摘出術をお勧めすることがありますので、専門医にご相談ください。
扁桃周囲膿瘍
急性扁桃炎が悪化して、口蓋扁桃の裏側に膿が溜まり、口が開きにくくなります。治療は抗生剤と併用して、扁桃の近くに針を刺して排膿あるいは切開排膿が必要なことがあり、悪化したケースでは入院治療をお勧めすることがあります。
さらに重症化して、首の深部に膿が及ぶ頸部膿瘍や、胸に膿が及ぶ縦隔膿瘍の状態になると命に係わる場合もありますので、適切な治療が望まれます。
さらに重症化して、首の深部に膿が及ぶ頸部膿瘍や、胸に膿が及ぶ縦隔膿瘍の状態になると命に係わる場合もありますので、適切な治療が望まれます。
慢性咽喉頭炎
急性咽頭喉頭炎をくり返す場合、または軽い咽頭喉頭炎の状態が続く場合などが考えられます。感染のコントロールや粘膜の状態を改善させる治療となります。含嗽薬、ネブライザーなどの局所治療、漢方薬などが有効なことがあります。
急性扁桃炎
口蓋扁桃(俗にいう扁桃腺)の急性炎症です。口蓋扁桃は口蓋垂(のどちんこ)の両脇にあるリンパ組織ですが、ウィルスや細菌感染などにより炎症を起こして赤く腫れます。悪化すると扁桃周囲炎・扁桃周囲膿瘍・頸部膿瘍に進展することもあります。抗生剤を中心に治療しますが、伝染性単核球症のようなウィルス疾患では敢えて使用しないケースもありますので、耳鼻咽喉科専門医での診察をお勧めします。
急性喉頭蓋炎
舌の奥にある喉頭蓋という部分が細菌感染などにより腫れる疾患です。悪化すると呼吸困難になり命にかかわるので、早めの対処が必要です。喉頭ファイバーですぐに診断でき、抗生剤を中心に治療しますが、緊急時は気管切開などの手術や救命処置を要することがあります。
鼻の病気
急性鼻炎
鼻かぜの状態ですが、治療は鼻内の掃除、ネブライザー療法(鼻から吸入する薬物療法)、内服薬などです。鼻汁が汚い場合は細菌の感染が疑われますので、抗生剤を使用することがあります。感染が蔓延すると急性副鼻腔炎を合併して、治療が長引くこともありますので、耳鼻咽喉科での処置をお勧めします。
アレルギー性鼻炎
ほこりやダニなどが原因の通年性アレルギーと、スギ花粉などが原因の季節性アレルギーがあります。ひどい場合は顔が真っ赤に腫れるなど皮膚症状を合併することがあります。アレルギーの原因物質に接触しないように工夫すること、抗アレルギー薬の内服、点鼻薬、漢方薬、ネブライザー療法などが治療となりますが、重症の場合は鼻粘膜焼灼術など手術的治療も適応となります。内服薬は、服用回数や眠気対策など人それぞれに合ったものを検討していきます。
薬剤性鼻炎
鼻づまりに使う血管収縮薬は点鼻薬の中でも即効性が高く、症状は一時的に改善します。しかし、これを多用し過ぎると鼻粘膜の状態がさらに悪化して薬剤性鼻炎の状態となり、症状がさらに重くなります。使用頻度を減らしながらステロイド点鼻薬と内服薬を中心に治療していきます。鼻炎の治療は症状とのバランスも大切ですので、耳鼻咽喉科専門医にご相談ください。
急性副鼻腔炎
鼻の奥にある副鼻腔に炎症が起こる病気で、急性鼻炎に引き続いて起こることが多いですが、副鼻腔が未発達の幼児はなりやすいと言えます。鼻汁、鼻づまり、額や頬の痛みなどが特徴ですが、悪化すると物が二重に見えたり目にも炎症が及ぶこともあり要注意です。治療は抗生剤、鼻水止め、鼻処置、ネブライザー療法などです。
慢性副鼻腔炎
副鼻腔炎が3か月以上続くものです。鼻汁、鼻づまり、後鼻漏(鼻汁がのどに落ちる)、額や頬の痛みなどが症状です。治療は抗生剤の少量長期投与療法、鼻処置、ネブライザー療法が中心です。経過が長いため急性副鼻腔炎に比べて治療に時間を要する傾向があります。鼻茸のある場合や薬で治りが悪い場合は、手術をお勧めすることがあります。
歯性上顎洞炎
上の奥歯の虫歯が原因で、近くの上顎洞(副鼻腔の一つ)に炎症を起こす病気です。虫歯の治療後に副鼻腔炎のような症状が続く場合などは歯性上顎洞炎が疑われます。耳鼻咽喉科と歯科の両方で診てもらう必要があり、治療は状態によってそれぞれ検討が必要です。
副鼻腔真菌症
鼻の奥にある副鼻腔にカビがついてしまう病気で、慢性副鼻腔炎のような症状をきたします。鼻内にカビの塊をみとめたり、レントゲン写真で片方の副鼻腔に影がある場合などに疑われます。飲み薬ではなかなか治らず、放置すると重症化することもあります。一般的には手術を検討します。
鼻茸
慢性副鼻腔などが蔓延すると、炎症のせいで粘膜が腫れてきて、副鼻腔から鼻腔に飛び出てきます。これは鼻茸または鼻ポリープと呼ばれます。鼻茸が大きくなると鼻づまりがひどくなります。飲み薬や点鼻薬で改善しない場合は、背景にある慢性副鼻腔も治療するために、手術をお勧めします。
鼻中隔弯曲症
左右の鼻を隔てる仕切り部分を鼻中隔と呼びますが、これが極端に曲がっていて鼻づまりをきたす状態を鼻中隔弯曲症と呼びます。成人の多くは多少曲がっており、症状がなければ治療の必要はありませんが、弯曲が強く症状もある場合は飲み薬や点鼻などで治療します。薬の治療でも効果がない場合には、手術も検討されます。
鼻出血
鼻の粘膜の血管からの出血ですが、原因はさまざまで、鼻が乾燥していたり、指で引っ掻いたり、アレルギー性鼻炎などで粘膜の状態が悪かったり、まれに腫瘍からの出血もあります。鼻の粘膜には血管が集中しており、また比較的浅いところを通るため、何もしなくても急に出血することがあります。
治療ですが、鼻の粘膜に薬品をつけて、あるいは電気凝固で止血する処置、軟膏ガーゼを留置する処置、などがありますが、出血の場所や状態によって治療法が選択されます。
出血の大部分は、鼻中隔(左右の鼻の仕切り)の前端部からですので、ご家庭でできる応急処置としては、坐位で下を向き、小鼻をつまんで圧迫するのが良いとされています。綿に軟膏を塗り鼻内に入れてから圧迫すると、より効果的です。鼻根部をつまんだり、うなじを叩いても効果がなく、上を向いたり血液を飲み込んだり寝転がったりすると逆効果です。
治療ですが、鼻の粘膜に薬品をつけて、あるいは電気凝固で止血する処置、軟膏ガーゼを留置する処置、などがありますが、出血の場所や状態によって治療法が選択されます。
出血の大部分は、鼻中隔(左右の鼻の仕切り)の前端部からですので、ご家庭でできる応急処置としては、坐位で下を向き、小鼻をつまんで圧迫するのが良いとされています。綿に軟膏を塗り鼻内に入れてから圧迫すると、より効果的です。鼻根部をつまんだり、うなじを叩いても効果がなく、上を向いたり血液を飲み込んだり寝転がったりすると逆効果です。
三叉神経痛
顔の知覚を司どる三叉神経の何らかの異常によって、特定の部位に鋭い痛みがおこる病気です。帯状疱疹や急性副鼻腔炎、周囲の血管による圧迫、その他いろいろな原因によると言われています。治療は神経痛の内服薬が中心となります。
鼻腔異物
鼻内に異物が入り混んだ状態です。こどもが遊んでいて鼻内におもちゃなどを詰め込んでしまうことがあります。取り出そうとして奥に詰め込んでしまうこともありますので、耳鼻咽喉科での摘出をお勧めします。また、異物を入れたまましばらく放置すると、鼻内で炎症を起こして黄色い鼻水が出てくることもありますので、異物が疑われる際は耳鼻咽喉科の受診をお勧めします。
嗅覚障害
原因として多いのは、鼻炎・副鼻腔炎の鼻づまりによって臭いの粒子が神経に届かないケースや、(風邪の後にもしばしば見られますが)臭いの神経がダメージを受けてしまったケース、などです。稀ですが脳の異常や腫瘍によって起こることもあります。原因によって治療法は異なりますが、鼻の炎症のコントロールや、においの神経を回復させる薬などを用いて治療を行います。
鼻前庭湿疹
鼻の入り口の皮膚に起こる炎症です。鼻のかみ過ぎやこすり過ぎ、鼻毛抜きでも起こる事があります。治療は軟膏を中心に、感染が疑われる場合は抗生剤を使用します。炎症の場所を極力触らないことが大切です。
鼻せつ
鼻前庭湿疹が皮膚の炎症であるのに対し、鼻せつは炎症が皮膚の下の結合組織にまで及ぶものです。治療は鼻内の安静と、抗生剤の内服、軟膏ですが、再発する場合は糖尿病などの基礎疾患についても調べる必要があります。
副鼻腔乳頭腫
ヒトパピローマウイルスというウイルスの感染でできた良性腫瘍ですが、稀に悪性化することがあります。鼻詰まり、頭痛、血液まじりの鼻汁など慢性副鼻腔炎に似た症状を起こします。診断は、鼻の内視鏡、レントゲン、組織検査などで行います。手術で腫瘍を取り除くのが一般的治療です。
副鼻腔悪性腫瘍
比較的まれな病気ですが、片側の副鼻腔炎に似た状態を呈します。同じ側から鼻出血が長期間続く場合にも疑うべき疾患です。治療は手術、化学療法(抗がん剤)、放射線を組み合わせることが多いです。
ウェゲナー肉芽腫症
鼻、耳、肺、腎臓などに障害を起こす免疫疾患です。鼻出血・鼻づまり・耳閉感などから疑われますが、血液検査などで診断され、薬物治療でコントロールしていきます。
流行性耳下腺炎(おたふく風邪)
ムンプスウィルス感染による耳下腺炎ですが、感染力が強く登校の制限なども決められています。稀ですが、ムンプス難聴という難治性の難聴にかかることがあります。おたふく風邪の治療は解熱剤などの対症療法が中心となります。
急性耳下腺炎
耳の下にある耳下腺に炎症が起きる病気です。原因は、おたふく風邪などのウィルス感染
、細菌感染、唾石症、その他の病気によるものなど様々です。原因に応じた治療が必要となりますので、専門医の受診をおすすめします。
、細菌感染、唾石症、その他の病気によるものなど様々です。原因に応じた治療が必要となりますので、専門医の受診をおすすめします。
亜急性甲状腺炎
甲状腺が炎症を起こし、のどの痛み、圧痛、嚥下時痛などが生じる病気です。ウィルスの関与が言われていますがはっきりしていません。血液検査などを元に診断し、炎症を抑える内服治療をおこないます。
アデノイド肥大(アデノイド増殖症)
鼻腔の突きあたりにある咽頭扁桃のことをアデノイドと呼びますが、口蓋扁桃と同じく咽頭の細菌などを退治する関門の一つとされています。アデノイド肥大は睡眠時無呼吸症候群や滲出性中耳炎などの原因となることがあり、アデノイド切除術をおすすめする場合があります。耳鼻咽喉科専門医にご相談ください。
上咽頭癌
鼻腔の突き当り付近である上咽頭にできる癌のことです。成人で滲出性中耳炎がある場合、上咽頭癌を除外することが大切です。鼻から内視鏡を入れて比較的容易に検査できます。
急性咽喉頭炎
いわゆる「のど風邪」とも言えますが、ウィルスや細菌感染などで咽頭や喉頭が炎症を起こした状態です。炎症を抑える薬など対症療法が中心ですが、細菌感染が疑われるケースでは抗生剤も検討されます。
急性扁桃炎
口蓋扁桃(俗にいう扁桃腺)の急性炎症です。口蓋扁桃は口蓋垂(のどちんこ)の両脇にあるリンパ組織ですが、ウィルスや細菌感染などにより炎症を起こして赤く腫れます。悪化すると扁桃周囲炎・扁桃周囲膿瘍・頸部膿瘍に進展することもあります。抗生剤を中心に治療しますが、伝染性単核球症のようなウィルス疾患では敢えて使用しないケースもありますので、耳鼻咽喉科専門医での診察をお勧めします。
慢性扁桃炎
急性扁桃炎をくり返す状態です。治療は抗生剤が中心ですが、基準以上に頻繁なケースでは口蓋扁桃摘出術をお勧めすることがありますので、専門医にご相談ください。
扁桃周囲炎
急性扁桃炎が悪化して、口蓋扁桃の裏側に炎症が波及した状態です。治療は抗生剤の内服や点滴が中心ですが、悪化して扁桃周囲膿瘍に進展すると入院治療をお勧めすることがあります。
慢性咽喉頭炎
急性咽頭喉頭炎をくり返す場合、または軽い咽頭喉頭炎の状態が続く場合などが考えられます。感染のコントロールや粘膜の状態を改善させる治療となります。含嗽薬、ネブライザーなどの局所治療、漢方薬などが有効なことがあります。
伝染性単核球症
EBウィルスという風邪ウィルスによって、急性扁桃炎や肝機能障害などを起こす病気です。大部分の方は、幼い頃にかかっていることが多く、知らないうちに卒業するのですが、思春期や大人になって初めて感染すると、強い症状を呈することがあります。抗生物質が逆効果のこともあり、専門医での診断・治療が必要です。症状が強い場合は入院をおすすめすることがあります。
急性喉頭蓋炎
舌の奥にある喉頭蓋という部分が細菌感染などにより腫れる疾患です。悪化すると呼吸困難になり命にかかわるので、早めの対処が必要です。喉頭ファイバーですぐに診断でき、抗生剤を中心に治療しますが、緊急時は気管切開などの手術や救命処置を要することがあります。
咽頭異物
咽頭に魚の骨がささったり、異物を飲み込んで引っかかってしまった状態です。口を開いて見える異物はつまんで取りますが、のどの奥の異物の場合は鼻から内視鏡を挿入し、先端から異物をつまむ器具を使って異物を除去します。
魚の骨がささった場合は、ご飯の丸のみをする方が多いですが、逆効果のこともありますのでおすすめしません。専門医を受診されてください。
魚の骨がささった場合は、ご飯の丸のみをする方が多いですが、逆効果のこともありますのでおすすめしません。専門医を受診されてください。
喉頭アレルギー
アレルギー症状が喉頭に起きることで、のどの痒み、異物感、乾燥感、から咳などの症状を出す状態です。アレルギーを抑える内服薬などで治療します。
咽喉頭異常感症
のどの違和感を感じる状態を咽喉頭異常感症あるいは咽喉頭神経症などということがあります。原因は様々ですが、咽頭炎の影響、副鼻腔炎での後鼻漏、逆流性食道炎、喉頭アレルギー、甲状腺疾患などの他に、身体表現性障害として心理的要因も大きく関わるケースもあります。原因に応じた治療が適応となります。
喉頭癌
声かれ、嚥下しにくい、のどに違和感がある、などが主な症状です。喉頭内視鏡検査で比較的容易に病気を疑うことができます。比較的治りが良い癌ですが、早期に耳鼻咽喉科専門医の受診をおすすめします。
口腔内真菌症
口腔内のカビが増えて粘膜が白くなる疾患です。生後2カ月頃に起こるカンジダ初感染は、自然治癒するのが普通ですが、成人ではうがい薬を中心に治療します。基礎疾患がある場合はそちらの治療も並行します。
逆流性食道炎
食道の圧がゆるんでしまい、胃液がのどの方に逆流することで、胸やけ、ゲップ、のどの違和感といった症状を起こす疾患です。咽喉頭異常感症の一因ともいわれます。診断的治療としてPPIテスト(胃酸を抑える内服薬を飲んで反応をみる)、また食生活や生活習慣の改善も必要となります。
咽頭腫瘍
咽頭には様々なタイプのできもの(腫瘍)ができる場合があります。稀に悪性で積極的治療を要することもありますので、耳鼻咽喉科専門医での診察をおすすめします。
顔・首の病気
顔面神経麻痺
顔の筋肉を動かすのが顔面神経ですが、ここに炎症が起きて神経が障害されることで顔の動きが悪くなる状態です。水痘・帯状疱疹ウィルスが関与すると言われているハント症候群、原因不明で比較的治りがよいベル麻痺、外傷や疾患による顔面神経麻痺などに分かれます。ステロイドなどによる早期の治療が大切ですので、耳鼻咽喉科専門医の受診をおすすめします。
ベル麻痺
何らかのウィルス感染によって顔面神経が障害され、顔の動きが悪くなる病気ですが、はっきりした原因は分かっていません。一般的には比較的治りが良いですが、麻痺が高度であったり、基礎疾患があったり、治療が遅くなると治りが悪いことがあります。耳の症状を伴うハント症候群よりは、治りが良いと言われています。治療はステロイドなどが中心ですが、専門医の受診をおすすめします。
ハント症候群
耳の発疹や難聴を伴った顔面神経麻痺をハント症候群といいます。水痘・帯状疱疹ウィルスが原因といわれていますが、抗ウィルス薬、ステロイドなどを中心に治療します。ベル麻痺より比較的治りが悪いと言われていますので、なるべく早期からの治療が大切になります。
急性耳下腺炎
耳の下にある耳下腺に炎症が起きる病気です。原因は、おたふく風邪などのウィルス感染
、細菌感染、唾石症、その他の病気によるものなど様々です。原因に応じた治療が必要となりますので、専門医の受診をおすすめします。
、細菌感染、唾石症、その他の病気によるものなど様々です。原因に応じた治療が必要となりますので、専門医の受診をおすすめします。
流行性耳下腺炎(おたふく風邪)
ムンプスウィルス感染による耳下腺炎ですが、感染力が強く登校の制限なども決められています。稀ですが、ムンプス難聴という難治性の難聴にかかることがあります。おたふく風邪の治療は解熱剤などの対症療法が中心となります。
亜急性甲状腺炎
甲状腺が炎症を起こし、のどの痛み、圧痛、嚥下時痛などが生じる病気です。ウィルスの関与が言われていますがはっきりしていません。血液検査などを元に診断し、炎症を抑える内服治療をおこないます。
頚部リンパ節炎(炎症性リンパ節腫脹)
首のリンパ節が炎症を起こして腫れる状態です。首から上の部分(耳鼻のど等)に細菌感染などが起こると、感染をくい止めようとして、首のリンパ節が炎症を起こして腫れます。特に、子どもはリンパ節も未成熟のため、より腫れやすい傾向にあるので珍しいことではありませんが、腫れが引かないとか、次第に大きくなってくる場合は、リンパ自体の病気も稀にありますので、専門医にご相談ください。治療は抗生剤の内服あるいは何もしないで経過をみることも多いです。
亜急性壊死性リンパ節炎
発熱と首のリンパ節の腫れが数週間つづく病気です。臨床経過や血液検査などで診断します。ウィルス感染が原因と考えられていますが、はっきりしていません。治療は解熱鎮痛剤などの対症療法が中心ですが、ステロイド内服を併用することがあります。
三叉神経痛
顔の知覚を司どる三叉神経の何らかの異常によって、特定の部位に鋭い痛みがおこる病気です。帯状疱疹や急性副鼻腔炎、周囲の血管による圧迫、その他いろいろな原因によると言われています。治療は神経痛の内服薬が中心となります。
頸部腫瘍
首にできる腫れものには、腫瘍(良性・悪性)、炎症性疾患など様々なものがあります。良性のものには、正中頸嚢胞、側頸嚢胞、甲状腺腫瘍、脂肪腫、線維腫、粉瘤、リンパ管腫、炎症性リンパ節腫脹などあります。悪性では甲状腺癌、頭頸部癌のリンパ節転移、悪性リンパ腫などがあります。すぐに診断可能な病気から精密検査が必要な病気まで様々ありますが、首が腫れた場合は専門医にご相談ください。
正中頸嚢胞
体の正中線でのど仏のやや上にできる腫れものです。胎児のころにあった、首の袋状の構造物が残ってしまった状態ですが、大人になってから気付くこともあります。感染を繰り返す場合や、見た目を重視する場合は、取り除く手術の適応となります。
側頸嚢胞
首の腫れもので、胎児のころにあった袋状の構造物が残ってしまった状態ですが、大人になってから気付くこともあります。感染を繰り返す場合や、見た目を重視する場合は、取り除く手術の適応となります。
耳下腺腫瘍
耳下腺は唾液をつくる臓器で耳の下にありますが、ここにできるのが耳下腺腫瘍です。画像検査、細胞診検査などで診断し、必要があれば手術をおすすめすることもあります。耳の下のしこりに気付いたら、専門医の受診をおすすめします。
顎下腺腫瘍
顎下腺は唾液をつくる臓器で顎の下にありますが、ここにできるのが顎下腺腫瘍です。画像検査、細胞診検査などで診断し、必要があれば手術をおすすめすることもあります。顎の下のしこりに気付いたら、専門医の受診をおすすめします。
甲状腺腫瘍
甲状腺は代謝に関するホルモンを作る臓器で、首の前面で鎖骨の上あたりにありますが、そこにできる腫瘍が甲状腺腫瘍です。大部分は良性ですが、稀に悪性もあり得るため、超音波検査、画像検査、血液検査、細胞診検査などで診断し、適切に対応することが必要です。
めまいの病気
メニエール病
めまい、難聴、耳鳴りなどを繰り返す病気で、内耳のむくみが原因とされています。心身のストレスが関係するとも言われており、若年から中年の女性に多くみられます。診断は主に問診と聴力検査でおこないます。早期の治療開始が望まれ、難聴がひどい場合はステロイドを用いることがあります。
良性発作性頭位めまい(頭位性めまい)
耳の奥の三半規管には位置感覚に関係する耳石が存在しますが、これが何らかの理由でズレることで生じるめまいと考えられています。難聴や耳鳴りを伴わない、数~数十秒の回転性めまいであり、頭を動かさないでじっとしていると治まり、動かすとまた起きることが特徴です。程度に個人差が大きいですが、めまいは時間がたつと治まってきます。症状がひどい時は内服や点滴を用います。
前庭神経炎
三半規管の情報を脳に送る前庭神経に何らかの炎症が起きて、持続的な回転性めまいを生じます。難聴や耳鳴りを伴いませんが、良性発作性頭位めまいとは違い、頭を安静にしてもめまいは軽快しません。安静が基本であり、症状がひどい時は内服や点滴を用います。
頸性めまい
首をひねると、内耳への血流である椎骨動脈が細くなり、血液が行かなくなるため起きるめまいです。画像検査で原因を調べますが、首をひねらない習慣も大切になります。
椎骨脳底動脈循環不全
小脳や椎骨脳底動脈の血液の供給が悪いことで起きるめまいです。めまいの他に神経症状がある場合は、この病気を疑う必要があります。頭部MRIなどで診断します。
起立性低血圧
起立時に脳への血液供給が少ないため、立ちくらみを起こす病気です。原因は、低血圧であったり、思春期で自律神経のバランスが未成熟な場合や、降圧剤、前立腺、安定剤などの薬剤の影響などが考えられます。血圧を測る検査で診断し、内服を中心に治療します。
脳脊髄液減少症
脳脊髄液が減ることで、起き上がる時などにふらつきや頭痛が生じる病気です。頭部外傷や出産後に起きることがあり、また神経症状も伴うことがあります。安静療法および注射など状態によって適切な治療が必要です。
その他の病気
睡眠時無呼吸症候群
睡眠中に呼吸がとまって、血液中の酸素量が減ることで、体にさまざまな悪影響を及ぼす病気です。昼間の眠気が強く、社会生活にも悪影響が生じます。また高血圧など生活習慣病や脳梗塞や心筋梗塞のリスクになり得ます。幼児では顎骨の発達障害、成長障害にも関影響します。診断は睡眠検査などで行い、重症度によって治療をご案内します。治療は、CPAP療法、手術、スリープスプリント(マウスピース)などの他、生活指導も大切です。耳鼻咽喉科専門医の受診をおすすめします。
のどの病気
急性咽喉頭炎
いわゆる「のど風邪」とも言えますが、ウィルスや細菌感染などで咽頭や喉頭が炎症を起こした状態です。炎症を抑える薬など対症療法が中心ですが、細菌感染が疑われるケースでは抗生剤も検討されます。
急性扁桃炎
口蓋扁桃(俗にいう扁桃腺)の急性炎症です。口蓋扁桃は口蓋垂(のどちんこ)の両脇にあるリンパ組織ですが、ウィルスや細菌感染などにより炎症を起こして赤く腫れます。悪化すると扁桃周囲炎・扁桃周囲膿瘍・頸部膿瘍に進展することもあります。抗生剤を中心に治療しますが、伝染性単核球症のようなウィルス疾患では敢えて使用しないケースもありますので、耳鼻咽喉科専門医での診察をお勧めします。
慢性扁桃炎
急性扁桃炎をくり返す状態です。治療は抗生剤が中心ですが、基準以上に頻繁なケースでは口蓋扁桃摘出術をお勧めすることがありますので、専門医にご相談ください。
扁桃周囲膿瘍
急性扁桃炎が悪化して、口蓋扁桃の裏側に膿が溜まり、口が開きにくくなります。治療は抗生剤と併用して、扁桃の近くに針を刺して排膿あるいは切開排膿が必要なことがあり、悪化したケースでは入院治療をお勧めすることがあります。
さらに重症化して、首の深部に膿が及ぶ頸部膿瘍や、胸に膿が及ぶ縦隔膿瘍の状態になると命に係わる場合もありますので、適切な治療が望まれます。
さらに重症化して、首の深部に膿が及ぶ頸部膿瘍や、胸に膿が及ぶ縦隔膿瘍の状態になると命に係わる場合もありますので、適切な治療が望まれます。
慢性咽喉頭炎
急性咽頭喉頭炎をくり返す場合、または軽い咽頭喉頭炎の状態が続く場合などが考えられます。感染のコントロールや粘膜の状態を改善させる治療となります。含嗽薬、ネブライザーなどの局所治療、漢方薬などが有効なことがあります。
急性喉頭蓋炎
舌の奥にある喉頭蓋という部分が細菌感染などにより腫れる疾患です。悪化すると呼吸困難になり命にかかわるので、早めの対処が必要です。喉頭ファイバーですぐに診断でき、抗生剤を中心に治療しますが、緊急時は気管切開などの手術や救命処置を要することがあります。
咽頭異物
咽頭に魚の骨がささったり、異物を飲み込んで引っかかってしまった状態です。口を開いて見える異物はつまんで取りますが、のどの奥の異物の場合は鼻から内視鏡を挿入し、先端から異物をつまむ器具を使って異物を除去します。
魚の骨がささった場合は、ご飯の丸のみをする方が多いですが、逆効果のこともありますのでおすすめしません。専門医を受診されてください。
魚の骨がささった場合は、ご飯の丸のみをする方が多いですが、逆効果のこともありますのでおすすめしません。専門医を受診されてください。
喉頭アレルギー
アレルギー症状が喉頭に起きることで、のどの痒み、異物感、乾燥感、から咳などの症状を出す状態です。アレルギーを抑える内服薬などで治療します。
咽喉頭異常感症
のどの違和感を感じる状態を咽喉頭異常感症あるいは咽喉頭神経症などということがあります。原因は様々ですが、咽頭炎の影響、副鼻腔炎での後鼻漏、逆流性食道炎、喉頭アレルギー、甲状腺疾患などの他に、身体表現性障害として心理的要因も大きく関わるケースもあります。原因に応じた治療が適応となります。
喉頭癌
声かれ、嚥下しにくい、のどに違和感がある、などが主な症状です。喉頭内視鏡検査で比較的容易に病気を疑うことができます。比較的治りが良い癌ですが、早期に耳鼻咽喉科専門医の受診をおすすめします。
亜急性甲状腺炎
甲状腺が炎症を起こし、のどの痛み、圧痛、嚥下時痛などが生じる病気です。ウィルスの関与が言われていますがはっきりしていません。血液検査などを元に診断し、炎症を抑える内服治療をおこないます。
扁桃肥大
俗にいう扁桃腺を正式には口蓋扁桃といいますが、口から入る細菌などを退治する場所です。人によって大きさが異なりますが、ただ大きいだけでなく、慢性的な炎症の場になっている状態(慢性扁桃炎)、あるいは睡眠時無呼吸症候群の原因になる場合は、口蓋扁桃摘出術の適応となることがあります。耳鼻咽喉科専門医にご相談ください。
逆流性食道炎
食道の圧がゆるんでしまい、胃液がのどの方に逆流することで、胸やけ、ゲップ、のどの違和感といった症状を起こす疾患です。咽喉頭異常感症の一因ともいわれます。診断的治療としてPPIテスト(胃酸を抑える内服薬を飲んで反応をみる)、また食生活や生活習慣の改善も必要となります。
咽頭腫瘍
咽頭には様々なタイプのできもの(腫瘍)ができる場合があります。稀に悪性で積極的治療を要することもありますので、耳鼻咽喉科専門医での診察をおすすめします。
口腔内真菌症
口腔内のカビが増えて粘膜が白くなる疾患です。生後2カ月頃に起こるカンジダ初感染は、自然治癒するのが普通ですが、成人ではうがい薬を中心に治療します。基礎疾患がある場合はそちらの治療も並行します。
喉頭肉芽腫
声帯の近くに腫れものができて、咽頭違和感や声かれなどの症状を起こします。逆流性食道炎も原因の一つといわれており内服薬などで治療しますが、治りが悪い場合は手術をおすすめすることがあります。
口腔内乾燥症
唾液が出にくく口内が乾燥した状態で、加齢に伴うものが最多です。ヒリヒリ感や味覚異常となることもあり、稀にシェーグレン症候群など全身疾患の可能性もあります。治療は、唾液腺のマッサージやガムを噛むことで改善する場合や、内服薬やうがい薬・スプレー剤を使用するケースもあります。
シェーグレン症候群
自己免疫疾患(自分の一部を他者と誤認する免疫異常)の一つですが、唾液・涙腺などの腺組織がやられてしまい分秘が悪くなる疾患です。つまりドライアイ・ドライマウスなどを呈しますが、治療は対症療法が中心となります。
唾石症
唾液をつくる三大唾液腺は、耳下腺、顎下腺、舌下腺ですが、この唾液腺の出口付近に石ができてしまい、唾液が出られなくなって唾液腺が腫れてしまう状態を言います。小さい石は自然に排出されることもありますが、腫れを繰り返す場合や石が大きな場合は、石を除去する手術が必要なことがあります。
声帯炎
喉の奥にある左右の声帯は、高速で振動することで声を作ります。声帯炎とは、この声帯が炎症をおこし嗄声(声がれ)などの症状を起こした状態です。大声を出し過ぎたり、風邪をひいて声帯の粘膜がむくむと、声がれなどの症状を起こします。治療は内服や吸入薬のほか、発声を控えることが重要になります。
声帯ポリープ
声帯の粘膜の一部がポリープ状に盛り上がり、声がれ(嗄声)を起こします。主に声の使い過ぎや喫煙などが原因と言われています。初期のうちは薬や発声を控えることで改善することがありますが、時間が経つなどして治りが悪い場合は、手術を要することがあります。
声帯結節
声を酷使すると、指のタコと同じように声帯にもしこり(結節)ができることがあり、これを声帯結節といい、声を酷使する職業に多い疾患です。初期のうちは発声を控えると改善することがありますが、長期間経過する場合は手術を要します。
反回神経麻痺
発声に関する神経(反回神経)が損傷し、声かれとなる状態です。
甲状腺腫瘍、肺や食道の腫瘍、解離性動脈瘤など、反回神経の走行部分の病変も疑われるため、喉頭ファイバースコープや画像検査といった精査が必要となります。
甲状腺腫瘍、肺や食道の腫瘍、解離性動脈瘤など、反回神経の走行部分の病変も疑われるため、喉頭ファイバースコープや画像検査といった精査が必要となります。
口内炎
口の中の潰瘍が原因で鋭い痛みが起こります。ヘルパンギーナ、手足口病などウィルスの病気で起こることもあります。ストレス、口内清潔、栄養状態が関係するとも言われます。繰り返す口内炎では、ベーチェット病など全身疾患の可能性もあります。治療はうがい薬、塗り薬、内服薬などです。
舌癌
初めは口内炎に似ていることも多いですが、硬めで比較的痛みが少ない特徴があります。
病変の一部を採取して病理検査することで診断されます。徐々に大きく硬くなる場合は、早期のうちに耳鼻咽喉科専門医への受診をおすすめします。
病変の一部を採取して病理検査することで診断されます。徐々に大きく硬くなる場合は、早期のうちに耳鼻咽喉科専門医への受診をおすすめします。
舌炎
舌の炎症でヒリヒリ感などの症状や味覚障害を起こすことあります。虫歯など口内の炎症、亜鉛など微量元素の不足、ビタミン不足、ストレスなどの影響も言われています。内服薬やうがい薬で炎症の治療をし、検査結果に応じてその他の治療をします。
味覚障害
舌の炎症、口内の炎症、亜鉛など微量元素の不足、ビタミン不足、嗅覚障害、薬剤性、中枢性など様々な原因が考えられますが、各種検査と原因に応じた治療を検討されます。